Twin's Story 2 "Bitter Chocolate Time"
《1 故障》
「ケ、ケン兄! イって、イって!」マユミが息を荒げて叫んだ。
ケンジとマユミは同じように身体を激しく波打たせ、クライマックスを迎えようとしていた。
「マ、マユっ! あああ、俺、も、もう……」ケンジはマユミを抱いた腕に力を込めた。そしてマユミの柔らかな胸に顔を埋め、呻いた。「で、出る! 出るっ!」
ケンジは身体を硬直させ、妹マユミへの熱い想いを、彼女自身の中に激しく放出させた。

二人の動きが止まり、マユミは愛しい兄の身体を抱きしめたまま満ち足りた気分で余韻を味わった。上になったケンジは、妹を抱きしめたまま、はあはあとまだ大きく喘いでいた。
やがて、二人はベッドに並んで横たわり、ケンジは優しくマユミの髪を撫でた。
「ケン兄、今日はなんだか激しかったね……」
「そうかな。イヤだったか?」
「ううん。あたしも燃えた」
「そうか。よかった」ケンジはマユミにキスをした。
「何かあったの?」
ケンジは少し考えてから言った。
「マユには隠さずに何でも言うことにする」
「隠すようなこと?」
「いや、お前の機嫌を損なうことかもしれない、ってとこかな」
「言って。大丈夫」
ケンジは躊躇いがちに口を開いた。「実は今日、アヤカにコクられた」
「アヤカ? アヤカって、ケン兄の水泳部のマネージャーだよね」
「そう。あいつだ」
「すっごい美人だよね、アヤカさんって。それにスタイルも良くてセクシーだし」
「何が言いたいんだ? マユ」
「で? OKしたの?」
ケンジは少しむっとしたようにマユミを横目で見た。「するわけないだろ」
「何で? だってアヤカさん、男子部員の憧れなんでしょ? あたしの学校の水泳部の男子も狙ってたよ、何人も」
「お前、俺がアヤカとつき合ってもいいのかよ」
「いや」
「だろ? だったら妙な揺さぶりをかけないでくれ」ケンジは口をとがらせた。
マユミはにっこり微笑んだ。「ケン兄なら大丈夫だね」そしてケンジの逞しい胸に頬を寄せて目を閉じた。まだ収まりきれないケンジの鼓動を聞きながら、彼女は自分の身体の火照りがゆっくりと冷めていくのを待った。
◆

ケンジの学校の水泳部マネージャーの中でもひときわ目を引く存在がアヤカだった。そのルックスもさることながら、丈が短く小さなタンクトップの脇から見える形のいい乳房、裾からちらりとのぞくへそ、ぴったりと腰に張り付いた真っ赤なショートパンツ。男子部員の志気を昂揚させるには十分すぎる格好で、いつも練習の時に動き回っていた。頭も切れ、スケジュール管理も部員の健康管理も他のマネージャー陣の追随を許さなかった。
「アヤカ抱きてー!」
「お前にゃ無理だよ。高嶺の花ってやつさ」
「高校生離れしてるよな、あいつのオーラ」
「内緒だけどな、俺、あいつの写真持ってるぞ」
「なにっ?!」
「時々それでヌいてる」
「エロ野郎め!」
そういう男子部員の会話が時々こそこそと繰り広げられる水泳部だった。
少し小太りの康男が、プールから上がった拓志に声を掛けた。「なあ、拓志」
拓志はキャップを脱ぎながらその友人に身体を向けた。「なんだ」
「最近思うんだが」康男は拓志に近づき、耳に口を寄せた。「アヤカって、異様にケンジに絡んでないか?」
「俺もそう思ってた。モーションかけてるんかね?」
「だけどケンジ、全然そんな気なさそうだけど」
「ま、当然だよな、あいつ、彼女持ちなんだから」
康男は肩をすくめた。「未だにあいつの彼女が誰だかわからねえんだが」
「だな」
「ほんとに付き合ってんのか? ケンジ」
「時々ケータイ見ながらニヤついてるのを俺は知ってる。あれはその彼女からのメールを読んでるのに違いないよ」
「今度こっそりヤツのケータイ見てやっか?」
「そうだな」
拓志と康男はにやりと笑って拳を軽くぶつけ合った。
――海棠ケンジ。17歳高二。
彼には双子の妹マユミがいた。実はこの兄妹は昨年の8月、ふとしたきっかけで恋に落ち、燃え上がる想いを爆発させて抱き合い、一つになった。そしてその関係は今も続き、二人はカラダを合わせ、愛し合って一つのベッドで眠る毎日を送っていた。もちろんその許されざる行為を知る者はいない。ただ一人を除いて。
その一人とは、二人が一線を越えてすぐの頃、ケンジの水泳部に部活留学でやって来ていた、関西弁を自在に操るカナダ国籍のケネス・シンプソンである。彼はこの兄妹が些細なことでケンカし、気まずくなっていたのを仲裁したことから、その事実を知ったのだった。だが、彼は日本にはいない。
「春の大会直前だぞ。海棠、お前何やってるんだ?」プールから上がったばかりのケンジに近づいてきたのは、水泳部の若いコーチだった。
「すいません」
「何かあったのか?」
「いえ、フォームを少し変えてみたんです」
「知ってる。見てた。そのことを言ってるんだよ」コーチは腕を組んで言った。「うまくいけば記録は伸びるかもしれん。が、お前にそれが合ってるかどうかってのは、ある意味賭けだ」
「ですよね」
「それに、」コーチの声が真剣味を増した。「下手をすると筋肉を痛める」
「え?」
「お前の腕の筋肉の付き方で、あのフォームには少し無理がある」
「そうですか……」
「向上心は認めるが、故障したらアウトだぞ」
「…………」
「しかも、もうすぐ大会だ。考え直せ」
「……」しばらくうつむいていたケンジは、顔を上げてコーチの目をまっすぐに見ながら言った。「明日までに答えを出します」
◆
風呂上がりに腕をさすりながら階段を上ってくるケンジを見つけて、マユミは部屋の前で彼を呼び止めた。
「ケン兄、腕、どうかしたの?」
「ん? いや、最近泳ぎ方を変えたんだ。筋肉の張り方が今までとは違う」
「え? だって春の大会明後日じゃん。直前になってそんなことしない方がいいんじゃない?」
「記録、伸ばしたいし」ケンジは言葉少なにぽつりとつぶやいた。
「マッサージしてあげようか?」
「え? い、いいよ、マユ」
「何赤くなってんの?」
「お、おまえに今、マ、マッサージしてもらったら、そのままなだれ込みそうだよ」
「いいじゃん、なだれ込んでも。だって、」マユミは恥じらいながら続けた。「あたし、明日の晩は学校の合宿所に泊まるから、ケン兄といっしょに眠れないよ……」
「そうか、マユ、明日は帰ってこないのか……」
「そんな悲しい顔しないで。一晩だよ、たったの」マユミは自分に言い聞かせるように言った。
ケンジはマユミの目を見つめてぽつりと言った。「一人で寝るの、寂しいな……」
「ほんとにぱんぱんだね。ケン兄の腕がこんなに硬くなってるのって初めてじゃない?」マユミは自分の部屋にケンジを招き入れ、彼の腕を両手で揉みほぐしながら言った。
「お前もそう思う? やっぱり俺にはだめなのかな、あのフォーム……」
「ケン兄に合ってないんじゃない?」
「コーチにも同じこと言われた」
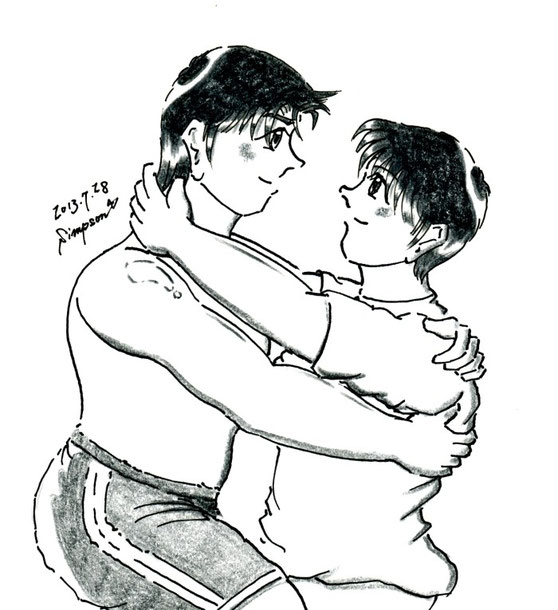
「無理しないで」
「ここんとこタイムが伸びてないから、俺、ちょっと焦ってた。明日、もう一回やってみて、だめだったら諦めるよ」
「それがいいよ」
マユミはそう言ってケンジの身体に腕を回し、キスを求めた。ケンジもマユミの背中に腕を回し、唇同士を合わせた。お互いの舌や唇を味わいながら、二人はマユミのベッドに移動し、着衣を脱ぎ去った。
「きて、ケン兄……」
「マユ……」
ケンジはマユミの頬を両手で優しく包み込んで、再び時間をかけて彼女の唇を味わった後、首筋、鎖骨、乳房へと舌を移動させた。「あ、あああ……。ケン兄……」ケンジの口がマユミの乳首を捉えると、彼女の身体がびくん、と反応した。
ケンジは右手の人差し指と中指をぺろりと舐めた後、マユミの秘部にあてがい、クリトリスをそっと撫でた。「あ、ああああ、身体が熱く、熱くなってる……」
そしてケンジの指がマユミの谷間に入り込む頃には、すでにマユミの中はじっとりと潤い、ケンジを受け入れる準備を整えていた。
「ケン兄……」マユミの手がケンジの分身を求めてさまよった。
「マユ……」ケンジが再びマユミの唇を自らの口でふさぐと、マユミは恍惚の表情でケンジの唇を味わいながらその手でケンジのペニスを自分の谷間に導いた。
「入れていい? マユ……」ケンジがマユミの耳元で囁いた。
「いいよ、ケン兄、来て」
ケンジはゆっくりとマユミの中に入っていった。「う、うううう……」
「あ、あああ、い、いい気持ち、ケン兄、ケン兄……」
ゆっくりと腰を動かし始めたケンジに合わせ、マユミもその柔らかな体を波打たせ始めた。そして次第にその動きは速く、激しくなっていった。
「う……くっ!」ケンジが喉から絞り出すような呻き声を上げた。
「イ、イって、ケン兄、あたしイきそう! 身体が熱い、熱いよ!」
「マ、マユ、マユっ!」ケンジの動きがいっそう激しくなった。「も、もうすぐっ!」
「ケン兄! あ、あたし、ああああ!」マユミの身体がのけぞった。「弾けちゃうっ!」
「お、俺もイくっ! 、マユ、マユっ!」
次の瞬間、いきり立ったケンジのペニスから強烈な勢いでマユミの体内に白く熱い想いが噴き出しはじめた。
「あああああ……!」マユミが叫ぶ。
「うううううっ!」ケンジも呻く。
二人は堅く抱き合ったまま同じように身体をびくびくと脈動させた。
◆
明くる朝、ケンジが起きて食卓についた時には、マユミはすでに出かけた後だった。ケンジははあっとため息をついて、コーヒーカップに手を掛けた
「マユ、今夜は合宿所だよね」
「そうよ」母親が言った。「あの高校は、春の大会直前は合宿所にみんな泊まることになってるからね」
「何で大会前なんだよ」ケンジは独り言のようにつぶやいた。
母親が怪訝な顔をケンジに向けた。「何? あんたに何か不都合でもあんの?」
「べ、別に」
「ケンジ、今日は遅くなるの? 部活」
「わからない。練習はそこそこで切り上げるだろうけど、ミーティングに時間がかかるかも」
ケンジはトーストにピーナッツバターを塗って口に運んだ。
「帰りが遅くなりそうなら電話してね」
「メールでもいい?」
母親は少し困ったように苦笑いをした。「あたしメールは気づかないかも。よかったら電話にして。できれば固定電話に」
「ちっ、めんどくさいな……」

その日の部活の時間、スタート台のケンジにアヤカが話しかけてきた。「海棠くん、調子はどう?」
「え? ああ、別に普通だけど」
「フォーム変えて、うまくいきそう?」
「知ってたのか」
「マネージャーだよ、私。それに海棠くんのことを私、一番気にしてるんだからね」アヤカの白い指がケンジの太股に軽く触れた。それが故意だったのか、偶然だったのかはケンジにはわからなかった。
「よーい!」ピッ。笛の音とともに、ケンジはスタート台から身を翻してプールに飛び込んだ。水中でのバサロの推進力はケンジのウリだった。スタート後の数秒で、誰よりも早く前に出ることができた。
ケンジは直感で今日の調子がいいことを悟った。最初のプルで水が身体の横をすり抜ける感触がいつもと違っていた。いつもよりスピードがアップしていることを実感した。
昨夜のマユミのマッサージのお陰かも、と思った時、左の二の腕に妙な違和感を感じた。しかし、どうしても新しいフォームを体得したくて、ケンジはさらに大きくリカバリーをした。
しかし、次の瞬間、左腕全体に激痛が走った。
「うっ!」あまりの痛みに、ケンジはその場に立ちすくみ、水の中に身を屈めて、左腕を押さえた。
「おい! ケンジの様子がおかしいぞ!」誰かが叫んだ。
「引き上げろ!」コーチも叫ぶ。「海棠くん!」アヤカの声も聞こえた。
プールに併設されたジムのレザー張りベッドに横になったケンジは、悔しさと腕の痛みに歯を食いしばっていた。額に大量の脂汗をかいている。
「大丈夫か、海棠」コーチがベッドの横に立って言った。
「す、すいません、コーチ……ううっ!」また腕に激痛が走った。
「無理するなって、言っただろ」
「…………」
「しばらく休んでろ。すぐに医務の先生が来るから」
「あ、ありがとうございます……」
「家庭に連絡してやる。今、家には誰かいるか?」
「い、いえ、俺、自分で連絡します。だ、大丈夫です。足と右手は普通なんで」ケンジはあわててそう言った。
コーチは肩をすくめた。
「そうか、じゃあお前が連絡しろ。早めにな」
「はい」
簡単な診察が済んで、ケンジの左腕にシップ薬を貼り付けながら医務担当の女性職員は言った。「それほどひどい怪我じゃないけど、痛みはしばらく残るかもね」
「あ、あの、大会は……」
「明日なんでしょ? その状態で出場する気?」
「無理……ですよね……」
「痛みだけじゃ済まなくなるわよ」
ケンジはうつむいてため息をついた。
「しばらくは、あまり動かさないようにするのよ」
「わかりました」
「痛みが引くまで少し横になってなさい。痛みが引かないようなら、一度病院で看てもらった方がいいかも。じゃあお大事に」
医務員はそこを出ていった。
一人、ベッドに残ったケンジは、マユミを想った。自分がフォームを変えてまで記録にこだわったのは、一つはマユミに自分の成長を見てもらいたかったからだ。それを思うと自分が情けなくて、自然と涙が溢れてきた。
その時、ジムのドアが開き、誰かが入ってきた。
「海棠くん、大丈夫?」アヤカだった。
「え? ああ」ケンジはあわてて涙を右手で拭った。
「気を落とさないで。みんながあなたの分までがんばってくれるよ」
「すまない、俺のわがままのせいで、大会に傷をつくっちゃって……」
「今はゆっくり怪我を治すことだけ考えて」
アヤカは毛布越しにケンジの胸にそっと手を置いた。
「そうそう、これ、栄養ドリンク。飲んで」
「え?」
「体力、落とさないようにしないといけないでしょ」
「ありがとう」

そう言えばかなり喉が渇いていた。起き上がると、アヤカが差し出したボトルをケンジはすんなり右手で受け取り、喉を鳴らしてごくごくと飲んだ。
「横になりなよ」アヤカは空のボトルをケンジから受け取ると、彼の背中に手を添えて、再び横になるのを手助けした。
「すまない、アヤカ」ケンジはゆっくりと横たわった。
「ねえ、海棠くん」アヤカが少し恥ずかしそうに口を開いた。
「何だ?」
「この前の返事……訊きたいんだけど」
「え?」ケンジは戸惑ったように表情をこわばらせた。
「私のこと……」
ケンジは思わずアヤカから目をそらした。
「アヤカ、すまない。俺、おまえとはつき合えそうにないよ」
「……それって、海棠くんには好きな人がいる、ってこと? それとも、もうつき合ってる……とか」
「い、いや、つき合ってる……っていうか……」ケンジは言葉を濁した。
「好きな人がいるってことだよね」アヤカはうつむいた。
「ごめん……」
「わかった。ごめんね、こんな時に変なこと聞いちゃって」
「いや……」
ケンジの頭がぼんやりとしてきた。横に立つアヤカの姿がなぜかぼやけて揺れ動き始めた。「何だか、今になって疲れが出てきたみたいだ」ケンジは強い眠気を感じ始めた。。
「いいよ。ゆっくり休んで」アヤカの言葉を聞きながら、ケンジはそのままうとうとと眠り始めた。




































