Chocolate Time 雨の物語集 ~雨に濡れる不器用な男たちのラブストーリー~
《2.初仕事》
すずかけ町のあるここK市は、県内でも比較的大きな都市で活気に溢れていた。駅近くの中央区は高層ビルや役所、税務署、警察署などの機関や新聞社、有名デパートなどが軒を連ねる大都会。一方そこから東に3㌔ほど離れた大きな一級河川を渡った先に位置する東区すずかけ町は、いわゆるベッドタウンと商業地区の中心で、大型ショッピングセンターやスイミングスクール、映画館などの娯楽施設も多い賑やかな町だった。

すずかけ町には有名な『Simpson's Chocolate House』があった。創業23年のこのスイーツ店は、カントリー風の温かで明るい木造の店舗と、プラタナスが立ち並ぶ駐車場を兼ねた前庭が特徴で、腕の良いメインシェフ、ケネス・シンプソンの作り出す魅力溢れるチョコレート製品の数々が数多くのリピーターを抱える人気店だった。広い店内の一角には喫茶コーナーもあり、手抜きを嫌う完璧主義者のケネスの手によるホットチョコレートやカカオ風味のコーヒーも絶品だった。人びとはこの店を『シンチョコ』と呼んで愛していた。
週明けの5日月曜日。遼はいつものように夜の8時に合わせて『シンチョコ』を訪ねた。
「遼君。いつもご苦労なこっちゃな」
ケネス(40)が出迎えた。
「ケニーさん、正月早々ずいぶん繁盛してますね」遼が店内を見回しながら言った。「さすがシンチョコ」
閉店時刻で、少し慌てながら商品を選んでいる初老の婦人と、喫茶コーナーから立ち上がった子ども連れの家族、それに数人の女子高生らしい女の子、レジに立った若い主婦が店内に残っていた。
レジに立ち、勘定を済ませた客に丁寧に頭を下げた、ケネスの娘でペットショップに勤めている真雪が、遼に気づいて声を掛けた。「秋月さん」
「やあ、真雪ちゃん。店の手伝い?」
「はい。ペットショップは明日からなんです」
「偉いね、ここ、手伝ってるんだね」
「パパは人使いが荒くて」真雪は悪戯っぽくウィンクをした。
「あほ。娘やったら当然や」ケネスが言った。
「はい、秋月さん、コーヒーどうぞ」
ケネスの妻マユミが遼を喫茶コーナーのテーブルに案内し、座らせた。
「あ、すみません、マユミさん」遼は帽子を脱いで椅子に腰を下ろした。
「パトロール、お疲れ様」
「いつもいつもごちそうしてもらっちゃって……」遼は申し訳なさそうに頭を掻いた。
最後の初老の婦人が店を出るのを見送った真雪が、テーブルに近づいてきた。
「秋月さんって、夏輝の実習指導員だったんでしょう?」
遼は意表を突かれたように顔を上げた。
「え? あ、ああ。そうだよ」
「夏輝がお世話になっちゃって」真雪はにこにこ笑いながら二つのチョコレートが載った小皿をテーブルに載せた。
「僕はほとんど何の指導もしてないよ。彼女は優秀だったから、僕はとっても楽だった」
真雪と夏輝は中学時代からの親友同士だった。
「夏輝、言ってました。すっごく紳士的で、相手のことを思いやる巡査長だ、って」
「そ、そう?」また遼は頭を掻いた。
「いろいろと相談にも乗ってもらったりして、『当たり』の指導教官だった、って言ってました」
「何やの、『当たり』って。失礼な言い方やな、ナッキーのやつ」
「いえ、ありがたいことですよ、ケニーさん」遼ははにかんだように微笑むと、コーヒーのカップを口に運んだ。
遼は夏輝の実習指導員の役目を終え、昨年末からこの地区のパトロール担当になっていた。そして必ず閉店時刻の夜8時に合わせてこの『シンチョコ』に立ち寄るのが日課になっていた。
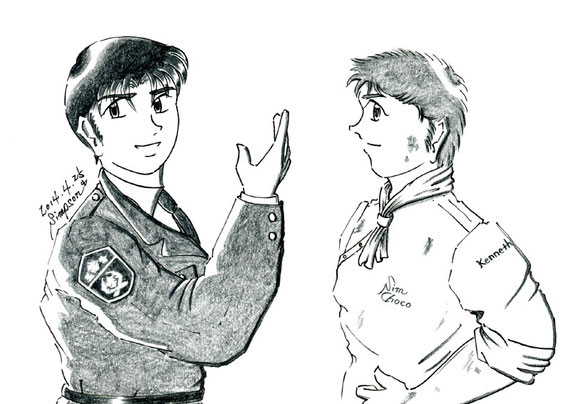
ケネスもカップを手に、遼と向かい合ってテーブルについた。
遼がカップをソーサーに戻して、ケネスに訊ねた。
「シンチョコって、ずいぶん前からこの街にありますよね。僕、子どもの頃から何度も来てました。親に連れられて」
「そやな。親父の代からやから、もう20年越えてるわな」
「すごいですね。もうすっかり街の顔になってますよね。チョコもコーヒーもおいしいし、店の雰囲気もいいし。それに、」遼は窓から外に目を向けた。「前の庭の木も立派で、歴史を感じます。プラタナスでしたっけ?」
「そや。偶然やけどこの街の名前といっしょやな。『鈴掛(すずかけ)の木』。この店建てた時に植えた時は、せいぜい今の遼君の背丈ぐらいやったかな」
「どうしてこの木を植えたんです?」
「親父はカナダ人やし、ちょっと西洋的な雰囲気にしよう、思てたんちゃうかな」
「確かに、少し日本離れした風情の庭ですね。この温かい感じの建物にもよく似合ってる」
「おおきに」ケネスは笑いながらカップを口に運んだ。
「通りの近くにある、あの木は、ひときわ立派ですね。」
「何や、あれだけ成長するのん、速くてなー。時々、あの木の下で人を待つ人間がおるわ」
「店のシンボルツリーってとこですか。きっと、今までたくさんの恋人達とかの待ち合わせ場所になってきたんでしょうね」
「近々ベンチでも置いたろかな、思てるねん」
「そりゃあいい! 街の人たちも喜びますよ、きっと」
遼はひどく嬉しそうにコーヒーをすすった。
◆
今年初めての出勤となる薄野亜紀(26)は、そのビルのエレベータを3階で下り、事務所のドアを開けた。
「おはようございます」
「やあ、亜紀ちゃん」
ロマンスグレーの社長が珍しく彼女に近づいてきた。
「あけましておめでとうございます。社長」
「うん。おめでとう」

社長の佐藤は穏やかに笑いながら少しだけ頭を下げた。
「今年もよろしくお願いします」
そう言って頭を上げた亜紀に、佐藤は小さな声で言った。「亜紀ちゃん、ちょっと社長室まで来てくれないかな」
「え? は、はい……」
亜紀は、佐藤の後について事務所の机の間を歩いた。窓際に座っていた営業部長の小林がその姿を舐めるように目で追っているのに気づき、亜紀は少し焦ったように足を速めた。
その夜、亜紀の会社の新年会が街の居酒屋で開かれた。
社員数20人程の小さな会社だったが、このところの不況の波をかぶり、業績はなかなか上向きになっていなかった。
亜紀は冴えない表情でその会が終わるのを何度も時計を見ながら待っていた。同僚が話しかけても、彼女はあまり明るい顔をしなかった。当然話は弾まず、彼女がハンカチで口元を拭いながら一礼すると、杯を持ってきた上司や同僚達はそそくさとその場を立ち去るのだった。
10時を回って、ようやく宴会が終わった。
居酒屋を出た所で、小林が亜紀に近づいてきた。ムッとするような酒の匂いをぷんぷんさせて、その頭頂の薄くなった小太りの男は亜紀の横にぴったりと立ち、耳に口を寄せた。
「社長にリストラの話、されたんだろう?」
亜紀ははっとして小林の顔を見た。その男は不敵な笑いを片頬に浮かべて、血走った目を亜紀に向けた。
「私が何とかしてあげようか?」
「えっ?」
「職を失うのはつらいだろう?」
「力になって下さるんですか? 部長さん」
小林は肩をすくめた。「お安いご用だよ」そして亜紀の背中を軽く撫でた。

「ちょっと歩こう。人には聞かれたくないんでね」
小林は人目を憚るように辺りを見回し、一人で行動しているように装って、先のコンビニの方に向かって歩き始めた。
ちらりと目線だけを送ってきた小林の向かった方に、亜紀も足を向けた。
亜紀は小林の後をついて歩いた。
「あ、あの、部長さん、どこへ?」
「いいから着いてきなさい」
小林は暗く狭い路地に入っていった。
急に小林が振り向いたので、亜紀はびっくりして足を止めた。
「薄野クン」
「は、はい……」
「君を会社に置いておく代わりに、僕の言うことを聞いてくれるね?」
まるで他に選択する余地はない、と言わんばかりの強引な口調だった。
「え? ど、どういうこと……」
小林は薄気味悪い笑みを浮かべて、亜紀の腕を掴んだ。
「あっ!」
「僕に今夜つき合ってくれれば、君が会社にとどまれるようにしてやろうじゃないか」
亜紀の背中を冷たいものが駆け抜けた。
「や、やめてください!」
亜紀は叫んだが、小林はさらに強く彼女の腕を掴んだ手に力を込めた。そして、身体を自分の方に引き寄せると背中にもう片方の腕を回した。
「いやっ! やめて!」
「言うことを聞くんだ! 会社をクビになってもいいのか?」
小林の顔が、亜紀の眼前に迫った。
その時!
「そこで何をしている!」
力強い男性の声がした。
小林は、弾かれたように亜紀の身体を解放した。
通りからその路地に向かって声を掛けたその若い警察官は、亜紀が佇んでいる所へ走り込んできた。
「りょ、遼……」亜紀はやっと聞こえるぐらいの小さな声でそう言うと、その警官の背後に回り、身を縮めた。

遼は酔って顔を赤くした男に身体を向けた。
「明らかに嫌がっていたようですが」
「わ、私は何もしていない……」小林は動揺したように目を泳がせた。
遼は亜紀に顔を向けた。「何かされましたか?」
「キスされそうに……なりました」
「他には?」
「この人に腕を掴まれて、無理矢理抱きつかれて……」亜紀の瞳に涙が宿った。
「本当ですか?」遼は再び小林に向き直った。
「ご、誤解だ……」
「事情をお訊きしてもよろしいですか?」
遼が小林に一歩近づいた時、その男は出し抜けにその若い警察官の横をすり抜け、猛スピードで駆け去っていった。
「本当に、他に何もされなかった?」遼は亜紀の目を見つめて言った。
「……うん」
遼はポケットからライトグリーンのハンカチを取り出したが、目の前のその女性に差し出すのを躊躇した。彼は亜紀に気づかれないようにそのままハンカチをポケットに戻した。その間に亜紀は自分のバッグからレースのハンカチを取り出し、瞳に堪った涙を拭いた。
「送っていくよ」
亜紀のアパートに着くまで、二人はほとんど何も言葉を交わさなかった。
亜紀のアパートの二階への階段の前で、彼女は遼に身体を向けてぎこちなく微笑んだ。
「あの……、どうも、ありがとう。助かった」そしてうつむいた。
「うん」
亜紀は、ふと顔を上げた。「あ、あの……」
「え?」
「気づいてくれて……嬉しかったよ」
「そうか……」遼は照れたように頭を掻いた。
「いつもあの辺りをパトロールしてるの?」
「う、うん。8時にシンチョコに立ち寄って、そこからアーケードを回ってぐるっとあの辺りまで。今日は公園の放置自転車の処理を手伝ってたから、ちょっと時間がかかったけど……」
「そう……。仕事、がんばってるんだね」
亜紀はぎこちない笑みを浮かべた。
「そ、それじゃ、僕はこれで」
遼は亜紀に一礼して、慌てたようにその場を離れた。
亜紀は去っていく遼の後ろ姿をずっと見つめていた。
亜紀の勤める会社では、その後、社長からも、他の上司からもリストラに関する話はなかった。ただ、部長の小林と顔を合わせたくなかった亜紀は、ずっと同じ課の同僚と行動を共にしていた。だが、小林も、あれ以来亜紀に近づくことはなかった。それでもその男は、時折亜紀のことを真顔でじっと見つめることがあった。亜紀はその度にあの背中を走る寒気を覚え、思わず席を離れるのだった。
◆
7日。水曜日。亜紀がシャワーを済ませた後、タオルで髪を拭いている時、ベッドの上に置いていたケータイが鳴った。
亜紀はそれを手に取り、ディスプレイを見た。登録されていない番号だった。
彼女は少し不安に駆られながら、受話ボタンを押した。
『亜紀ちゃん?』
電話の向こうで明るく弾けるような声がした。
「え?」
『俺だよ、俺。省悟』
「省悟? え? あ、狩谷くん?」
『良かった。まだ覚えててくれてよ』
狩谷省悟(26)。現在この街を中心に宅配便のドライバーをやっている青年だった。彼と亜紀、それに遼とは同じ高校の同級生同士だった。

「どうしたの? いきなり」ケータイを耳に当てたまま亜紀はベッドに腰掛けた。
『ごめん、勝手におまえの電話番号、友達に教えてもらっちゃって。びっくりしただろ?』
「いいよ。気にしないで。で、何か用だった?」
『明後日の同窓会、来るんだろ?』
「え? 同窓会?」
『そうだよ。通知来てなかったか? おまえに』
亜紀は昨年末に届いていたはがきを思い出した。明後日の土曜日、駅近くの中華料理店で高校時代の同窓会が開かれるという案内だった。
亜紀は同窓会で遼と顔を合わせるのも気まずかったし、友人達に遼とのつき合いのことについてあれこれ訊かれるのも面倒だったので、そのままにしておいたのだった。
「はがきは……見たけど……」
『おまえ、近くに住んでんだろ? 来いよ。久しぶりに話そうぜ』
省悟のその底抜けに明るい声を聞いて、亜紀は心が少しずつほぐれていく感じがした。同時に会社でのもやもやした気分を吹き飛ばしたいという気にもなっていた。
「そうだね。返事してなかったけど、行ってもいい?」
『もちろんだ。待ってっぞ。絶対来いよ、絶対だからな』
亜紀は笑いながら言った。「狩谷くんったら、張り切り過ぎだよ」




































