Chocolate Time 雨の物語集 ~雨に濡れる不器用な男たちのラブストーリー~
『雨の歌』 (1.穏やかな出会い|2.突きつけられた真実|3.気づかなかった想い|4.雨の歌|5.アクアマリンのリング)
《1.穏やかな出会い》
その男は、床に敷かれたピンクのボーダー柄のカーペットの上にあぐらをかき、一人用のベッドの横に置かれた小さなテーブルの上にあった白い焼酎の瓶に手を掛け、スクリューキャップをひねった。
玄関脇の狭いキッチンから女が氷を入れたグラスを運んできて、男の前に置いた。
男は顔を上げて女を見た。「おまえも飲めよ」
女は手にハイボールの缶を持って、男の隣に座り、身を寄せた。
「あたしは無理。よくそんなの飲めるね」
「炭酸で割って、レモン入れて飲んでみろよ。けっこういけるぜ」
「遠慮しとく。あたしその匂いがだめだもん」
男は氷の入ったグラスに焼酎をどぼどぼと注いで、すぐに口に持って行った。
ここは女の住むワンルームマンションだった。テレビのモニターにはヴィジュアル系バンドのライブが流れ、騒々しいサウンドを部屋中にまき散らしていた。
男は女の肩を抱き、唇を突き出して女の顔に迫った。女はそれに応え、二人は激しく口同士を重ね合い、舌を絡め合った。
「あんたのキスは野性的で最高だよ」口を離した女は笑いながらそう言った。「焼酎の匂いが邪魔だけど」
「彼氏のキスじゃ満足できねえのか?」
「全然物足りない。っていうか、あの人にキスされるの、あたしあんまり好きじゃない」
「エッチは?」
「エッチも何か普通すぎてね。あんたに乱暴されながらじゃないと、あたしイけない」
「彼氏はイかせてくれねえのかよ」
「あの人からイかされたことなんか、今まで一度もないよ。いっしょにイったふりをしてるだけ。でも、」
「ん?」
「彼のクンニはなかなか感じる」
「そうなのか?」
「でも、それでも満足しないけどね。」女は後ろに手を突き、軽く伸びをして笑った。
「へえ」男はまた焼酎のグラスを口に持って行った。「そんなやつと、よくつき合ってんな。おまえ」
「だって、少なくとも稼ぎは安定してそうだし。女遊びなんかしそうにない人だし」
「おまえ、結婚する気なのか?」

女は少し考えてから言った。
「プロポーズされたら、うん、って言うかも」
「なんだよ、それ」男は呆れ顔をした。「じゃあ、俺はそん時捨てられんのかよ、おまえに」
「結婚しても、抱いてよ」
「はあ?! おまえ、自分が言ってること、わかってんのか?」
「だって、あんたの方が、エッチは百倍気持ちいいもん」
「勝手なヤツ……」
男は腰を上げた。「タバコ吸っていいか?」
「外で吸ってよ」女は窘めるようにそう言って、自分のハイボールの缶を慌てて飲み干し、男に渡した。「はい。吸い殻入れ」
「済まねえな」男は玄関ドアを出て行った。
しばらくしてドアを開けた男は、狭い玄関に脱いだ自分の靴の脇に、手に持っていた灰皿代わりの缶を置き、女の元に戻るなりシャツを脱ぎ始めた。
「よし、じゃあやるか」
「うん」女は顔を赤らめた。
◆

天道良平(29)は、風呂上がりの髪をタオルで拭きながら、リビングのソファで新聞を読んでいた弟に声を掛けた。
「修平」
「何だ? 兄貴」
良平はソファの後ろに立って弟の修平(26)を見下ろした。
「おまえ、リサさんと同級生なんだろ? 春日野(かすがの)リサ」
「リサ? ああ。そうだけど。なんで兄貴が知ってんだ?」
「最近俺の店に新しく入ってきたんだ」
「へえ」修平は、読んでいた新聞をたたんでセンターテーブルに置いた。
良平はテーブルを挟んで修平と向き合って座り、眼鏡のレンズをティッシュで拭き始めた。
「どんな子なんだ?」
「おっとり系だな」
「確かにそんな感じだ」
「だけど、けっこう正義感も強いし、芯がある」
その時、修平の妻夏輝がリビングにコーヒーを運んできた。「良平兄さん、どうぞ」そして、その義理の兄の前にカップを置いた。
「ありがとう、夏輝ちゃん」良平は夏輝を見上げて微笑んだ。「夏輝ちゃん、修平との結婚生活、どう?」
良平の弟修平と夏輝は、高三から6年のつき合いを経て、一昨年の12月に結婚した。
「楽しいですよ」修平の横に座った夏輝は笑いながら言った。「毎日が変化に富んでて」
「何だよ、変化に富んでて、って」修平が横目で夏輝を見た。
「だって、そうじゃない。あんた思いつきで何でもやるし」
「そういう性分なんだよ。兄貴と違ってな」
良平は笑った。「確かに修平は僕と随分性格は違うね」
そして彼はコーヒーカップを手に取った。
「良平兄さんと結婚してたら、もっと穏やかでゆったりとした毎日が送れてたかも」
「夏輝っ! おまえ兄貴と結婚しようなんて思ってたのかよ!」
「何言ってんの。喩えよ、喩え」
良平は大笑いした。「ホントに賑やかな毎日を送ってそうだね」
修平が言った。「そうそう、リサのことについちゃ、夏輝の方が詳しいんじゃね?」
「リサ? リサがどうかしたの?」
「ああ。兄貴の店に就職したって」
「そうなんだ」夏輝は顔をほころばせた。「奇遇だね」
良平はカップを持ち上げた。「面接の時に言ってたんだ。修平と夏輝ちゃんと同じ高校だったって」
「リサなら大丈夫だね、修平」
「そうだな。真面目で仕事はきっちりやるタイプだかんな」
「そうか」良平は満足したようにコーヒーを飲んだ。「3月生まれ、って履歴書に書いてあったけど。ってことは、君たちの中では一番年下ってわけ?」
「小柄でふわふわした感じでしょ? あの子」夏輝が言った。「でも、意外に芯が強いところはありますね」
「修平も今、そう言ってたな」
「理性的だけど、愛想は抜群にいいやつだよ。客相手の商売には向いてると思うぜ」
良平兄弟の母親がリビングにやってきて、チョコレートの乗った銀色のトレイをテーブルに置いた。
「すまないねえ、夏輝ちゃん。いつもおみやげ持ってきてもらっちゃって……」
「とんでもない。あたしこそ、お義母さんに大したこともできなくて、すみません」
「いいのよ。それより修平、」
「何だよ、母ちゃん」チョコレートをつまみかけた修平が意表を突かれたように動作を止めた。
「あんた、夏輝ちゃんのお母さん、大事にしてるんだろうね?」
「ったり前だろ。母ちゃんあっての夏輝なんだからな。って、兄貴はまだ結婚しねえのかよ」修平は良平の顔を見た。
良平は少し黙り込んだ後、顔を上げて母親に笑いかけた。「すぐに、ってわけじゃないけど。少しは考えてる」
掛けていた眼鏡を外した良平は、恥じらったようにまたコーヒーを口に運んだ。そして、独り言のように呟いた。「もう30になるわけだし」
◆
良平は街外れのホームセンターに勤めていた。大学を出てすぐ就職し、7年目を迎えた現在は販売部長を務めている。
その日、良平は店内を巡回しているとき、ペットコーナーで、客を相手ににこやかに小犬の説明をしているリサの姿を認めた。彼女は客の話に耳を傾けながら、犬の種類とその性質、飼い方などを笑顔を絶やすことなく、丁寧に解説していた。
良平がその傍らを通り過ぎるとき、リサは小さく会釈をして、良平に目を向けた。
良平も小さくうなずくと、その場を離れた。
夜、閉店間近に再び巡回をしていた良平は、リサが子猫のケージの前にじっと佇んでいるのを見つけ、声を掛けた。
「春日野さん」
リサは少しびっくりしたように肩を揺らして、良平に振り向き、慌てたように目元を拭った。
「あ、天道部長」
良平はリサに近づいた。「どうしたの?」
リサはばつが悪そうにうつむいた。
「何か、仕事で辛いことでもあった?」良平は心配そうに訊いた。
「い、いえ。大丈夫です」
「悩みがあるのなら、聞いてあげてもいいですけど……」

「はい……」リサは顔を上げて良平を見た。
リサの視線に瞳を射抜かれ、良平は唾を飲み込んだ。
「私、最近、つき合ってた人と別れたんです」
良平は少し動揺して目をしばたたかせた。
小さなため息をついて、リサは言った。「それだけです」そして彼女はにっこりと笑った。
「辛かったですね……」良平は自分がまるでそんな目にあったかのように悲しい顔をした。
「すみません、部長。こんなプライベートなことで、仕事を疎かにしちゃうなんて……」
「いや、貴女はちゃんと仕事をこなしてますよ。普通以上に」
「ありがとうございます」リサはまた穏やかに笑った。失恋の苦しさを抱えているにもかかわらず、その笑顔は人に癒しを与えてくれるような温かさだと良平は思った。
「元気出して」良平もにっこりと笑った。
勤務が終わり、事務所を出た良平は、ケータイを取り出して耳に当てた。
「今、仕事が終わったんだ。これからすぐ行くよ」
それだけ言って、彼は通話を切り、小走りで従業員用駐車場に向かった。
◆
その部屋はこぎれいなワンルームマンションだった。
良平は三階の一番端にある部屋の前に立って、呼び鈴を押した。
すぐにドアが開き、ピンクのスウェット姿の女性が顔を出した。「良平! 待ってたよ。上がって」
良平は狭い玄関で靴を脱いだ。そして振り返ってつま先を外に向けようとしゃがんだとき、玄関の傍らに空になった白い瓶とハイボールの空き缶が置かれているのに気づいた。
部屋のテレビから派手なロックのリズムと、ヴォーカルの絶叫が聞こえる。
「沙恵、君は焼酎も飲むようになったのか? ハイボールは前から飲んでたけど」
部屋に入って上着を脱ぎながら、良平はベッドに座った恋人沙恵(24)に問いかけた。
沙恵は小さく舌を出して良平を見上げた。「最近飲むようになったんだよ。レモン入れて炭酸で割って飲むの。おいしいよ」
「俺の前では一度も飲んだことないだろ、そんなの」
「友達に教わって飲んでみたらおいしくて。病みつきになっちゃったんだ」
沙恵は髪をブラシで梳きながら屈託のない調子で声を弾ませた。
「それにしても、いつの間に一本も空けたんだ?」
「だって……」沙恵は声を落とし、床のカーペットに座った良平の横に来て身体を密着させた。「良平、なかなか来てくれないじゃない。あたし、寂しかったんだから……」

良平は沙恵の肩に手を置き、もう片方の手で沙恵の顎を持ち上げて、唇を重ね合わせた。
ほのかにタバコの匂いがした。
そっと口を離した良平は、沙恵の髪をそっと撫でながら、耳元で囁いた。「ごめん、寂しい思いをさせちゃって……」
良平はぎゅっと沙恵の身体を抱きしめ、カーペットの上に横たえると、その身体を彼女に覆い被せ、腕をつっぱったまま彼女の瞳をじっと見つめた。
「沙恵……」
「良平、来て……」
良平は眼鏡を外してネクタイを抜き、シャツのボタンを焦ったように外した。
下着姿になった良平は、うっとりと顔を上気させた沙恵の身に着けていたスウェットを脱がせ、同じように下着姿にした後、ゆっくりと身体を重ね合わせた。
沙恵と熱いキスをしながら、良平はブラのホックを外し、溢れた乳房を両手で揉みしだいた。
んんっ、んっ……
沙恵は口を塞がれたまま、喉の奥で呻いた。
ベッドに沙恵を横たえた良平が言った。「沙恵、テレビ消してくれないか?」
「どうして?」
「こういう騒々しい音楽は、俺、どうも苦手で……」
「えー、かっこいいじゃん。V系バンドの歌」
沙恵は口をとがらせて枕元のリモコンのボタンを押した。部屋が突然の静寂に包まれた。
全裸になった沙恵の秘部を時間を掛けて唇と舌で愛撫しながら、良平はバッグからライトブルーのパスケースを取り出し、挟まれていたプラスチックの包みを手にした。そして、それを破って中に入っていた薄いゴムを取り出すと、自分のいきり立ったものに被せた。
「良平、来て、早く来て!」
「いくよ、沙恵」
良平は再び沙恵の口を吸った。沙恵は一瞬目を開き、眉の間に皺を寄せ再び目を閉じた。
良平のペニスが沙恵の中に入り込むとき、沙恵の身体が一度ビクン、と小さく跳ね上がった。
良平はリズムをつけて沙恵の中で動いた。そしてしだいに息を荒くしていった。
沙恵も良平の背中に腕を回し、喘ぎながら身体を同じように上下に揺すった。
「さ、沙恵! イ、イく、イくよっ!」
「良平!」
沙恵の爪が良平の背中に食い込んだ。同時に良平の身体の奥から熱く沸き立ったものがペニスに被せられたコンドームの中に放出され始めた。
「んっ! んっ! んんっ!」良平は身体を仰け反らせて、苦しそうに歯を食いしばり、その脈動が収まるのを待った。
「ああっ!」沙恵が叫び、良平の背中に回されていた腕が解かれ、力なくシーツの上に落ちた。

シャワーを浴び、沙恵と良平は全裸で一人用の狭いベッドに並んで横になっていた。
「久しぶりで、いっぱい感じちゃった……」沙恵は照れたようにそう言って良平の首に腕を回した。
「そう。良かった」
良平はにっこり笑った。そして彼女にキスをしようとした時、沙恵が小さな声で言った。「ねえ、良平、あたしといつ結婚してくれるの?」
良平は意表を突かれたように数回瞬きをした。「え?」
「一人でいるの、寂しいよ」
「ごめん。もうちょっと待てる? 俺もこの仕事長いから、来年あたり、昇格する予定だから」
「来年……」
「ほんとにごめん。もう少し我慢してくれ」
「……うん」
良平は沙恵といっしょに大きな枕に頭を沈めた。
「そう言えば」良平が仰向けになって天井を見つめながら口を開いた。
「なに?」
「圭輔君、今月で仕事辞めるんだ」
沙恵は横目でちらりと良平を見た。「圭輔君が?」
「うん。どんな事情かはわからないけど……」
「そうなんだ……」
沙恵は良平と同じように天井に目を向けた。
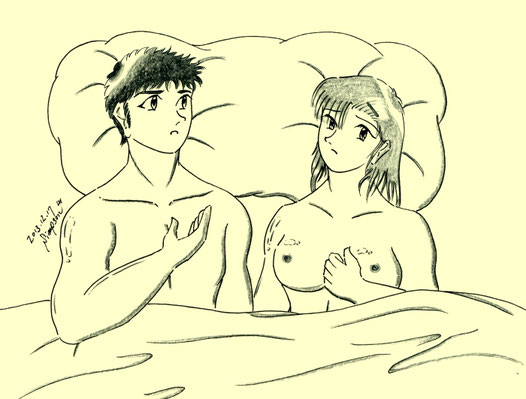
「彼は働き者だったし、手放すのは惜しいんだけどね」
「あたし、あの人苦手だったな」
「どうして?」良平は頭を傾けて沙恵の顔を見た。
「なんか、上から目線で話すし、タバコ臭いし」
「タバコ?」
「あたし、良平のホームセンターでバイトしてた時、休憩の後のあの人の息が我慢できなかったもん」
「そうだったんだ」
「それが理由であたしバイト辞めたってわけじゃないけどね」沙恵は笑った。
「今の仕事はどう?」
「コンビニって、けっこう仕事がマニュアル化されてるから、あれこれ考えなくて済むのは楽かも」
「でも、お昼時とか忙しいんだろ?」
「想定内の忙しさだからね。人から言われる程大変じゃないよ」
「そうか。身体壊すなよ、沙恵」
「うん。ありがと」
良平は沙恵の身体に腕を回した。
「あ……」沙恵は小さく声を上げた。
「沙恵……」良平は抱いた腕に力を込めた。
沙恵は身体を固くして良平から顔を背けた。
「沙恵?」
「今、危ない時期なんだ。」
「大丈夫だよ、ゴムつけるから」
「……ちょっと疲れてるんだ。ごめんね、良平」
良平は沙恵の目を見つめた。彼女は瞳を泳がせた。
「そうか……。ごめん、無理させちゃって」
「良平も仕事で疲れてるんでしょ?」
「沙恵と会えば疲れなんて忘れるよ」
「ふふ。嬉しい、良平」
「来週、君の誕生日だね」
沙恵は少し動揺して、困ったように眉を下げた。「お、覚えてくれてたんだね」
「当たり前だろ」良平は呆れたように笑った。「誕生日の夜は来られないけど、その次の土曜日にプレゼント持ってくるよ」
「ホントに? 嬉しい!」
それから、二人は静かに、じっと抱き合ったまま朝を迎えた。
雨の歌 1.穏やかな出会い|2.突きつけられた真実|3.気づかなかった想い|4.雨の歌|5.アクアマリンのリング
ホーム|Chocolate Time シリーズ 本編第1期 本編第2期 外伝第1集 外伝第2集 外伝『雨の物語集』 外伝第3集|Chocolate Time シリーズ総合インフォメーション





































