Twin's Story 外伝 "Hot Chocolate Time" 第2集 第11話
《男の矜恃タイム》

〈4.修平の矜恃〉
下町にある古い長屋風の食堂街。その狭い路地を入ったところにある、行きつけの『おたふく』という大衆食堂に、修平は夏輝を連れ込んだ。魚を焼く煙とタバコの匂い、それににわか雨のような揚げ物の音が騒がしい客の話し声と共に店の中に充満していた。
がふがふがふ! 遠慮なく派手な音を立てて、丼飯を口に掻き込んでいる修平を、夏輝は呆れ顔で見つめていた。
修平は手を止めて、目を上げた。
「夏輝、おまえ全然食ってねえじゃねえか。腹減ってねえのかよ」
「修平見てたら、お腹一杯になった」夏輝は微笑んだ。
修平は肩をすくめて夏輝の前の玉子丼に手を伸ばした。「食わねえんなら、よこせ」
がふがふがふ! 修平は二杯目の丼を口に豪快に掻き込んだ。
夏輝はそんな修平の顔をずっと見つめていた。

少し煮詰まった豆腐とわかめの味噌汁を一気に口に流し込んで、脂ぎってぎらついたテーブルに並べた二つの空の丼の横にその碗を置いた修平は、コップの水を一気にごくごくと飲み干すと怪訝な顔で夏輝を見た。「気持ちわりいな。何だよ。じろじろ見やがって……俺の顔になんかついてっか?」
「ごはんつぶが山のようについてるよ」夏輝は笑って、テーブルの紙ナプキンを修平に手渡した。
「済まねえな」
「おしっ! 腹も一杯になったことだし、出るか」修平が伝票を持って立ち上がった。「心配すんな。ここは俺が持つ」
「って、あんたしか食べてないでしょ」
「何にしろ、それが男の矜恃ってもんだ」
夏輝は噴き出した。「男の矜恃ねえ……」
修平は爪楊枝をくわえたままレジで代金を支払った。
「ごっそさん! また来っからな、おばちゃん」
「いつもありがとさん!」でっぷりと太った背の低い、三角巾を頭につけたおばさんが、にっと笑って修平と夏輝を交互に見た。「また二人でいっしょにおいで!」
週末の賑やかな通りを修平と夏輝は並んで歩いていた。
「泊まっていけんだろ?」
「うん……」
「ちょっとコンビニ寄るぞ」修平はそう言って、丁度通りかかったところにあったコンビニに入っていった。夏輝も後に続いた。
修平は特製冷やし中華を迷わず選んでかごに入れた。
「まだ食べるの? 修平」
修平はそのまま無言で店内を歩き、飲み物の並べられた大きな冷蔵キャビネットの前に立った。そしてガラスの扉を開けながら夏輝に顔を向けた。「何が飲みたい?」
「え? あんたんちにあるものでいいよ。わざわざ買わなくても……」
「俺のアパートに今ある飲み物は蛇口から出るモンだけだ」
「な、なによ、それ……」
「ビールとか?」修平は缶ビールを手にとって夏輝を見た。
「なんで飲み物がビールになるんだよ」
「だっておまえ、すでに大人だろ?」
「え?」
修平は自分の後頭部に手を当てた。「すまねえ、夏輝。二十歳の誕生日に何もしてやれなくてよ」
「……修平」
「飲むか?」修平がまた訊いた。
夏輝はふっと笑った。「修平が追いつくのを待つよ。あんたの誕生日にいっしょに乾杯しよ」
修平はにっと白い歯を見せて笑った。「そうだな」
「ジンジャーエールでいいよ。あんたも好きでしょ」
「わかった」
◆
修平のアパートは決して新しいとは言えない建物だった。
「何か、いつもより片づいてるね。修平、掃除したんだ」
「ったりめえだろ。彼女を泊めるんだ。それが男の、」
「矜恃ってもんだ、でしょ?」
「そ、そうだ」修平はばつが悪そうに頭を掻いた。
「『矜恃』なんて難しい言葉、どこで覚えたの?」
「最近な。教育学の授業で出てきたんだ。ちょっとかっこいいから俺、マスターした」
「へえ。感心じゃん」夏輝は笑った。
修平はコンビニの袋からさっき買った特製冷やし中華を取り出して小さなテーブルに置いた。
「よし、食え、夏輝」
「え? あんたが食べるんじゃなかったの?」
「丼二杯も食って、さらに腹に入るわけねえだろ。いいから食えよ。おまえの好物だろ、それ」
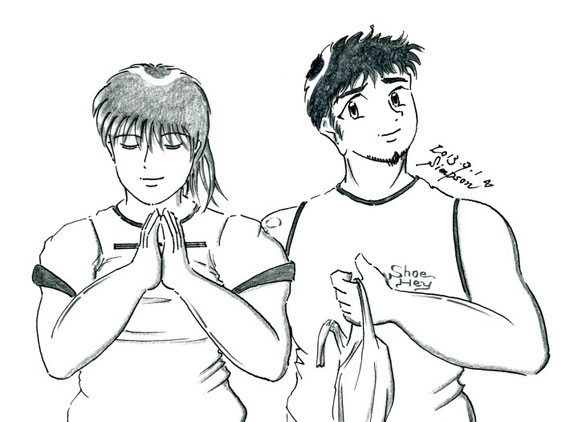
しばらく修平の顔を見つめた後、夏輝は数回瞬きをして小さな声で言った。「ありがとう、修平。いただきます」
夏輝は静かに手を合わせて割り箸を二つに割った。
修平は食べ始めた夏輝の横顔をしばらくじっと見つめた後、立ち上がって食器棚からコップを二つ取り出してテーブルに置いた。そして買ってきたジンジャーエールを注いだ。
「やっと効いてきたな、エアコン。どうにか涼しくなったな」修平は呟いた。
「先にシャワーいいぞ」夏輝が食べ終わった容器を元の袋に入れながら修平が言った。
「修平……」夏輝は物言いたげな目で修平を見た。その瞳にはうっすらと涙が浮かんでいた。
「ほら、入っちまいな。俺も汗かいてんだ」
「う、うん……」
夏輝はバッグから着替えを取り出して、狭いバスルームに入っていった。
夏輝の後にシャワーを浴びた修平が、ボクサーショーツ一枚でタオルで髪を拭きながらバスルームから出てきた時、同じように下着だけの姿の夏輝が出し抜けに彼にしがみついた。
「修平! 修平修平修平!」
「な、夏輝?!」
「抱いて! 修平、あたし、もう我慢の限界」
修平は夏輝の身体を抱き返し、そのまま一人用のベッドに倒れ込んだ。
ベッドに横たわった夏輝は焦ったように自分でブラのホックを外した。そして修平の頭を抱えて自分の胸に顔を押し当てた。
むぐ……。修平は小さく呻いてそのまま再びゆっくりと夏輝の背中に腕を回し、静かに力を込めて抱きしめながらその乳首に舌を這わせた。
「あ、ああん……」
夏輝の息はすでに荒くなっていた。
修平は身体を一度起こして下になった夏輝の身体を愛しそうに眺めた後、彼女の頬をそっと両手で三度撫でてから、ゆっくりと唇を彼女のそれに触れさせた。

今まで修平が夏輝に一度もしたことのない、甘く柔らかなキスだった。
夏輝は目を潤ませた。
「夏輝……」
「修平……」
「好きだ、夏輝……」
修平は長く、壊れ物を扱うように夏輝の唇を吸い、舐めた。夏輝の身体の中で熱い流れが渦巻き始めた。
修平の手が夏輝のショーツにかかり、ゆっくりと脱がされた。修平も自分の下着を脱ぎ去った。そして夏輝の身体を包み込むように抱いた。
「ああ……修平……」
修平はまたついばむように夏輝の唇を吸った後、舌を滑らせ、首筋、鎖骨、乳房へと移動させた。そして左手で夏輝の右の乳房をさすりながら左の乳首を舐め上げた。
「修平……あああ……」
修平の口が、夏輝の股間に埋められた。
「ああっ!」夏輝の身体がビクン、と硬直した。
修平の舌と唇がすでに雫を溢れさせている谷間を舐め、襞を挟み込み、吸った。それも今までにない静かな愛撫だったが、夏輝はいつになく身体をよじらせて激しく喘いだ。「しゅ、修平! ああああーっ!」
「修平! 来て! あたしと一つになって! お願い! お願いっ!」
夏輝は叫んだ。
「夏輝、いいのか?」
「来て、来て! そのまま……」
「ゴム、つけなくていいのか?」
「大丈夫、今は大丈夫。だから早く来て、修平!」
修平は大きくなってびくんびくんと脈動しながら、先端から糸を引いた透明な液をまき散らしているペニスを手で掴んで夏輝の秘部に押し当てた。
「修平っ! 修平っ!」
修平はゆっくりと腰を動かし、少しずつ夏輝の中にペニスを入り込ませた。
二人の身体がぴったりと重ね合わされ、深く繋がり合ったことを確認した修平は、何度も顔を交差させ直し、夏輝の唇を味わいながら、腰の動きを次第に大きく、速くし始めた。
「んん……んんっ」
二人の身体中に汗の粒が光っている。
ベッドが激しく軋む。
修平の口に塞がれた夏輝の口から、それでも大きな呻き声が漏れる。
修平はおもむろに口を離した。
「な、夏輝、夏輝っ! イ、イく、出る、出るっ! ぐうううっ!」
「イって! 修平、あたしの中に来て! 修平、修平っ! あああああーっ!」
がくがくがく……。二人の身体が同じように大きく痙攣した。
びゅ、びゅるるっ!
「んぐうううっ!」「ああーっ!」
どくどくどくっ! どくっ! どくっ!
修平と夏輝は同じようにぶるぶると身体を震わせながら、お互いの心地よい身体の熱さに酔いしれた。

「夏輝……」
「修平、ごめん……」夏輝はそう言って修平の手をぎゅっと握りしめた。
「夏輝……俺の方こそごめん。おまえに寂しい思いをさせちまって……」
「修平……」
「それに、せっかくの誕生日も祝ってやれなかったし……」
「いいんだよ、修平。今年のあたしの誕生日を今日ってコトにするから」
夏輝の目から突然涙が溢れ始めた。「修平、ごめん、ごめんなさい、あたし、あたし……」
「夏輝?」
「許して、修平……」夏輝の涙はとどまることなく溢れ続けた。
修平はうろたえた。「な、夏輝、泣くな、俺の前で泣かないでくれ。おまえらしくねえだろ……」
「うん、うん。ごめん、ごめん、修平……」
修平は夏輝の身体をぎゅっと抱きしめた。その温かく大きな胸の中で夏輝はいつまでも涙を溢れさせていた。
◆
狭い、申し訳程度のバスタブに修平と夏輝は抱き合ってはまり込んでいた。
「夏輝ー……。こんな狭い思いしてまで二人でシャワーしなくても……」
「修平とくっついていたいんだ、あたし」
「そうなのか……。ほら、顔洗え。涙でぐしゃぐしゃじゃねえか。」修平は夏輝にシャワーのノズルを手渡した。
「ごめん、ありがとう」夏輝は顔をごしごしと洗った。
「相変わらずがさつな洗い方だな。みっともねえだろ? 二十歳になったんだからよ、もっとこう、優雅に洗えねえもんかな」
「これ、死ぬまで変わらないよ。たぶん。」夏輝は照れたように笑った。

修平は夏輝からノズルを受け取って、タオルで夏輝の顔をそっと拭った。
「いつになったら話せる?」
「え?」
「何かあったんだろ?」
「……うん」
「待っててやっから、おまえが話したくなったら言え」
「ありがと、修平。ちゃんと言う。このあとすぐに……」
修平は躊躇いながら小さく言った。「おまえをこうやって……抱いててもいいのか? これからも……」
夏輝は慌てて顔を上げた。
「し、心配しないで。修平。大丈夫。あたしこれからもずっと修平の彼女だから。それは心配しないで」夏輝は修平の手を握りしめた。「もう離すことはないから。大丈夫……」
「そうか……」
修平は安心したようにため息をついた。
「ごめん、心配かけて」
「気にすんな」
修平は両手で夏輝の頬を包み込み、そっとキスをした。
◆
「秋月巡査長」
夏輝が熱い緑茶の入った二つの湯飲みを持って、秋月のデスクにやって来た。
「日向巡査」
実習指導員秋月遼巡査長は、夏輝を見上げてにっこり笑った。
一つの湯飲みを秋月の前に置いて、夏輝も微笑んだ。
秋月は、湯飲みに手を掛けた。「今日は調子良さそうですね。以前よりもかえって元気そうに見えますよ」
「そうですか?」
「何か嬉しいことでも?」
夏輝は恥ずかしげに数回瞬きをした後、少し首をかしげてその上司の警察官を見た。「はい。秋月巡査長のお陰です」
「僕の?」
「はい」夏輝はまたにっこりと笑った。
少しの間を置いて秋月もふっと笑った。「そうですか。それはよかった」
「あ、そうそう」
夏輝はポケットからアイロンがきれいにかけられ、きちんとたたまれたハンカチを取り出した。「遅くなっちゃいました。これ、お返しします」
それは、あの夜、秋月が夏輝に貸してくれたものだった。
「あの時は、本当にどうもありがとうございました」
夏輝はぺこりと頭を下げた。

秋月はそれを微笑みながら受け取ると、湯飲みの日本茶を一口すすった。「8時から巡回パトロールです。準備しといてくださいね」
「はい」
夏輝は立ち上がった秋月に近づき、耳元で囁いた。「もう大丈夫。巡査長の前では弱音を吐きません」
秋月は囁き返した。
「そうしてください。僕の前ではね」そしてぱちんとチャーミングなウィンクをした。
「ペットボトルのお茶、今日はあたしが準備しときます。」
「そう? じゃあお言葉に甘えて」
秋月はまた白い歯を見せてにっこりと笑った。
2013,11,22(2014,1,2) 脱稿
※本作品の著作権はS.Simpsonにあります。無断での転載、転用、複製を固く禁止します。
※Copyright © Secret Simpson 2013-2014 all rights reserved

『男の矜恃タイム』あとがき
ご存じの通り『Chocolate Time』シリーズの本編エピソード10では、主人公の真雪が妻子ある男性と過ちを犯してしまい、その後恋人龍と共に苦しみ、しかし二人で乗り越える、という出来事を描きました。その中で、真雪の中学来の親友夏輝が彼女を慰め、元気づける中で語った自分自身の体験が今回のこのエピソードです。
男女(とは限りませんが)の恋愛期間中には、いろいろな危機があって、もしかしたらそれが元で別れなければならなくなったり、逆に結びつきがより強くなったりするものですが、真雪と龍の場合も、今回の夏輝と修平の場合も、結果的には後者に落ち着きます。
愛する女性が「揺らいだ」事実を知って、龍も修平もおそらくひどく動揺するのですが、どちらも「この人を放したくない」という気持ちが強く、でもどうしていいかわからない、といったぎこちなさが態度や言葉に出るものです。もっとも男性によっては、でんと大きく構え、そんなことで俺たちの関係が壊れるわけないだろ、と堂々としている強者もいるのでしょうが、作者である僕自身が、やっぱりそういった目に遭えばおろおろするだろうし、どうしたら彼女の心を掴み直すことができるのだろう、とくよくよ悩んだりするだろうことは想像に難くありません。だから僕が紡ぐ物語の中の男性も、やはりどうしてもそういうタイプになってしまうわけです。
高校時代の修平はとてもやんちゃで跳ねっ返りで、こと夏輝の前では強がりを言ったり開き直ったりするような弾けた男子でしたが、大人に近づいた今、ぎこちなくも恋人夏輝を包みこむような行動を取ることができるようになっているようで、なかなかに微笑ましいです。夏輝もこの夜の修平を評して、「それまでで一番優しく抱いてくれた」と真雪や春菜に語っているほどです。
さて、男なら「据え膳食わぬは男の恥」という喩えもある通り、女性に少しでも脈有りと思えば、何とかして落としたいと思うものですが、いやあ、この秋月巡査長、なかなかのジェントルマンですね。もちろん彼自身がすごく真面目で誠実な性格だということもあるのですが、実はこの時、彼の心を占有している女性がいたというのが、彼が魅力的な若い女性警察官を前にしてさえ思いとどまることができた一番の要因です。その女性とは、彼も話の中で語っていた高校時代からつき合っていて別れてしまった元彼女のことです。
秋月巡査長は、やがてこの彼女とよりを戻すのですが、それはもう少し先の話です。
Simpson
男の矜持タイム 1.実戦実習 - 2.揺れる気持ち - 3.秋月の矜恃 - 4.修平の矜恃
ホーム|Chocolate Time 本編第1期|本編第2期|外伝第1集|外伝第2集|外伝『雨の物語集』|Chocolate Time シリーズ総合インフォメーション



































